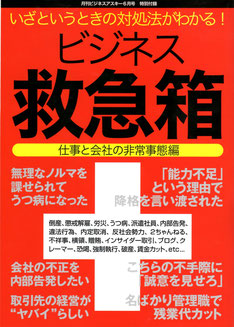派遣先均等・均衡方式Q&A
派遣先均等・均衡方式に関するQ&A ▽令和元年12月26日厚生労働省公表
▼比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供
Q1.労働者派遣法第 26 条第 7 項に「派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない」とあるが、派遣労働者1人が複数の業務を行う場合(労働者派遣契約の業務内容に複数記載されている場合等)、それぞれの業務ごとに比較対象労働者を提供する必要があるか。
A1.複数の業務を行う派遣労働者の場合、仮に一の業務の比較対象労働者の待遇に関する情報だけ提供を受けても、正確に派遣労働者の待遇を決めることができないおそれがある。
このため、業務の内容が複数あるときは、原則、その業務ごとに比較対象労働者の待
遇に関する情報を提供することが必要である。
Q2.複数の業務を行う派遣労働者については、それぞれの業務ごとに比較対象労働者を提供することが必要とのことだが、例えば、A業務及びB業務を行う派遣労働者の場合、A業務の比較対象労働者とB業務を行う比較対象労働者の待遇で共通するものもある。その場合も、業務ごとにすべての情報を提供する必要があるのか。
A2.原則は、A業務を行う比較対象労働者及びB業務を行う比較対象労働者の待遇に関する情報を、業務ごとにすべて提供する必要があるが、共通する待遇については、いずれか一方を提供することで他方は省略しても差し支えない(例えば、A業務の比較対象労働者の情報を基本とし、B業務のみに適用される手当等を付加的に提供する方法でも差し支えない)。
ただし、省略する場合には、省略する旨と当該共通する待遇の参照箇所を明記すること。
また、待遇の種類が共通している場合であっても、実施基準が異なる場合は、それぞれ提供が必要なこと。
Q3.派遣労働者が従事する複数の業務が、比較対象労働者と一致している場合、まとめて一の比較対象労働者の情報を提供すれば足りるか。
A3.従事する複数の業務が一致している場合、一の比較対象労働者の情報提供で法第 30条の3の均等・均衡待遇の義務の履行が可能と考えられるものであれば、その対応で差し支えない。
Q4.法第 26 条第 7 項に「派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない」とあるが、一つの労働者派遣契約で複数人を同職種(業務)に派遣する場合、一の比較対象労働者の提供でよいか。
A4.一つの労働者派遣契約で複数人の派遣労働者を同職種(業務)に派遣する場合、派遣労働者らが行う職務の内容等が同一で、同一の比較対象労働者の待遇に関する情報の提供で、法第 30 条の3の均等・均衡待遇の義務の履行が可能と考えられるものであれば、一の比較対象労働者の情報提供で差し支えない。
なお、その際、派遣元事業主及び派遣先との間で十分な調整を行い、派遣労働者らが行う職務の内容等が同一であることを確認すること。
Q5.労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ派遣先の比較対象労働者の待遇に関する情報の提供をしなければならないが、すでに派遣労働者Aに係る比較対象労働者の待遇に関する情報の提供をしている中で、その契約期間中に新たに派遣労働者Bについて派遣労働者Aと同一の内容(同一の派遣先、組織、業務内容等)で追加契約を締結する場合も改めて比較対象労働者の待遇に関する情報の提供が必要なのか。
A5.貴見のとおり。ただし、派遣労働者Aの契約期間中であれば、「令和○年○月○日付けの情報提供から変更がない」旨を書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより、派遣労働者Aに係る労働者派遣契約の締結に当たって提供された比較対象労働者の待遇に関する情報(その後変化がないものに限る。)を、派遣労働者Bの労働者派遣契約の締結に当たって、比較対象労働者の待遇に関する情報を提供したものとして差し支えない。
なお、書面の保存等については、紛争防止の観点から一定の保存期間を定めており、派遣労働者Bの労働者派遣が終了する日が派遣労働者Aより後になるのであれば、派遣労働者Bの労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
Q6.労働者派遣契約の更新も法第 26 条第 7 項の「労働者派遣契約を締結するに当たって」に該当し、改めて比較対象労働者の情報提供が必要なのか。
A6.貴見のとおり。ただし、比較対象労働者及びその待遇に関する情報に変更がない場合には、更新時に改めて同一の情報を提供する必要はなく、「令和○年○月○日付けの情報提供から変更がない」旨を書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより、派遣先から派遣元事業主に提供することで差し支えない。
Q7.比較対象労働者の選定に当たって、例えば「職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者」の区分に複数の労働者が該当する場合、労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日施行版)第6の2(3)ハ(ロ)では「派遣労働者と同一の事業所に雇用されているかどうか」等の観点で、選定することになっている。ここでいう「同一の事業所」とは「派遣労働者が実際に就業する場所」という理解でよいか。
A7.ここでいう「同一の事業所」とは、「派遣労働者が実際に就業する場所」を包含する事業所のことを指すものである。
Q8.「仮想の通常の労働者」も提供できない場合(「一定の根拠」を示せない場合等)、「仮想の短時間・有期雇用労働者」を比較対象労働者として提供することは認められるのか。
A8.認められない。
Q9.比較対象労働者の待遇の実施基準として、賃金テーブルを提供する場合、情報提供の時点では実在する労働者がいなくても、当該賃金テーブルの該当箇所を示すことで情報提供することも可能か。また、その際は、実在しない労働者であるため、「仮想の通常の労働者」と整理されるのか。
A9.お尋ねのような情報提供でも可能である。
就業規則が情報提供の時点で有効であり、対象となる者を雇い入れた場合に適用され、
就業規則に基づく待遇が確保されるのであれば、労働者の標準的なモデルとして認められることとなる。
Q10.比較対象労働者が1人の場合、個人を特定されるおそれがあるが、比較対象労働者の待遇に関する情報を提供する場合は、当該個人に対して事前に承諾などを取った方がいいのか。
A10.比較対象労働者の選定の優先順位により、下記①~⑤のいずれかに該当する比較対象労働者が1名のみであり、当該比較対象労働者1名のみに係る待遇等の情報提供を行うこととなった場合において、比較対象労働者が一定の個人に特定されるおそれがある場合には、当該比較対象労働者の意向を踏まえ、比較対象労働者の待遇等の情報を提供する際に、個人が特定されないよう、労働者の標準的なモデル(※)としての待遇情報を提供すること等の配慮を行うことが望ましいこと。
※ 現存する就業規則等に基づき設定され、適用実績のあるもの。例えば、「新入社員、勤続○年目の一般職」など。
【比較対象労働者の選定の優先順位】
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
② ①に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
③ ①及び②に該当する労働者がいない場合にあっては、業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
④ ①~③に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
⑤ ①~④に該当する労働者がいない場合にあっては、①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
⑥ ①~⑤に該当する労働者がいない場合にあっては、派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者
Q11.比較対象労働者の区分が「一人の労働者」であって、その者が育児や介護等の「家族的責任を有する労働者」である場合、そのような情報も含めて提供するべきなのか。
A11.家族的責任を有する労働者であって、個々の待遇を決めるに当たって配慮したことがあれば、「待遇決定に当たって考慮した事項」欄にその旨を記載すること又は家族的責任がなかった場合に適用される標準的な待遇の内容を記載することが必要である。
ただし、個人やその家族の情報が特定されないよう、待遇の差を中心的に記載し、家族の状況等の記載は必要最小限にすることが必要。
Q12.労働者派遣法施行規則第 24 条の4第1号ハに「当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)」とあるが、「主な待遇」とは具体的に何を指すのか。
A12.主な待遇とは、省令上に例示されている昇給及び賞与に加え、例えば、ガイドライン(※)に定める基本給、各種手当(「役職手当」、「特殊作業手当」、「特殊勤務手当」、「精皆勤手当」、「時間外労働に対して支給される手当」、「深夜労働又は休日労働に対して支給される手当」、「通勤手当及び出張旅費」、「食事手当」、「単身赴任手当」、「地域手当」、「福利厚生施設」、「転勤者用住宅」、「慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障」、「病気休職」、「法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇」、「教育訓練」及び「安全管理に関する措置及び給付」)、退職手当、住宅手当及び家族手当を指す。
※ 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する
指針(平成 30 年厚生労働省告示 430 号)
Q13.人事制度が途中で変わる可能性がある。当初通常の労働者Aが比較対象労働者として最も近い労働者としていたが、その後通常の労働者Bが最も近い比較対象労働者となった場合、労働者Bを比較対象労働者として情報提供を行わなければならないのか。
A13.比較対象労働者が変わった場合も、待遇に関する情報に変更があった場合に該当する。したがって、他の項目に変更があった場合と同様に、改めて、かつ、遅滞なく情報提供を行う必要がある。
Q14.労働者派遣法施行規則第 24 条の6第3項において、「労働者派遣契約が終了 する日前1週間以内における変更であって、当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を変更しなくても法第 30 条の3の規定に違反しないもの」については、情報提供が不要とされている。しかし、待遇の内容によっては、1週間以上前の変更であっても派遣労働者の待遇に影響がないこともある。その場合も、変更時の情報提供をすることが必要なのか。
例:出張旅費の変更だが、派遣労働者が出張しないことが明らかな場合。
例:通勤手当の上限が引き上げられたが、派遣労働者がその上限に届かないことが確実な場合。
A14.例示にあるような出張旅費や通勤手当であっても、1週間以上前の変更であれば、労働者派遣契約期間中に経営方針や家庭状況の変化等により支給されることとなる可能性も否定できない。そのため、変更時の情報提供が必要となる。
▼派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置
Q1.派遣先均等・均衡方式の均衡待遇の場合、退職手当はどのように派遣先の通常の労働者と比較すればよいか。
A1.派遣先均等・均衡方式の均衡待遇においては、基本的に、全ての待遇が含まれるものであり、退職手当についても、派遣先の通常の労働者との間で均衡を確保する待遇の対象となる。
そのため、退職手当の支給の有無が不合理な待遇差であるか否かは、派遣労働者と派遣先の通常の労働者のそれぞれの職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該退職手当の性質及び目的を照らして適切と認められるものを考慮して判断される。
この「その他の事情」には、事業主と労働組合との間の交渉といった労使交渉の経緯などの諸事情が想定されるものであることから、労使で十分に議論していただくことが望まれる。
▼待遇に関する事項等の説明
Q1.「雇入れ」時と「派遣」時が同じタイミングである場合、労働者派遣法施行規則第25条の16 に定める共通する事項はまとめて明示等をすれば足りるか。
A1.貴見のとおり。
Q2.法第 31 条の2第3項の「労働者派遣をしようとするときは」の範囲は、別企業なのか、別の最小組織単位なのか。組織単位が同じで業務が変わる場合も該当するのか。
A2.法第 31 条の2第3項の「労働者派遣をしようとするとき」は、組織単位が変わる場合や組織単位が同じで業務が変わる場合も該当する。
▼福利厚生施設、就業環境の確保等
Q1.ある派遣労働者の従事する業務には更衣室が必要なく、当該業務に従事している通常の労働者も同様の実態にある場合には、他の業務に従事している通常の労働者が更衣室を利用しているからといって当該派遣労働者に更衣室の利用の機会を与える必要はないという理解でよいか。
A1. 貴見のとおり、当該派遣労働者に更衣室の利用の機会を与える必要はないことが通常であること。
Q2.法第 40 条第3項の福利厚生施設の利用機会の義務について、派遣先は派遣労働者に対して、「給食施設の料金」を通常の労働者と同じ条件で利用させなければならないのか。
また、給食施設の料金を同じにする場合に費用負担が発生することが想定されるが、派遣元事業主と派遣先のどちらが負担するのか。
A2.法第 40 条第3項の福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)については、派遣先が「利用の機会を与えなければならない」と規定されており、ご指摘の「給食施設の料金」が同額でないという事実のみをもって当該規定に違反することとはならない。
ただし、派遣先の労働者と派遣労働者で「給食施設の料金」の差が大きいことなどに
より、結果として、派遣労働者が給食施設を実質的に利用できない状況となっている場
合には、派遣先の義務違反となり得る。
一方、「給食施設の料金」は、法第30条の3(派遣先均等・均衡方式)の待遇に含まれるため、派遣元事業主は「給食施設の料金」について、派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡を確保しなければならない。
このため、派遣先は、派遣料金の設定に際して、派遣労働者に係る「給食施設の料金」の負担分を考慮するなどして、義務違反とならないよう適切にご対応いただくことが必要。
 東 社会保険労務士事務所(千代田区飯田橋) ご相談窓口 03-3265-3335
東 社会保険労務士事務所(千代田区飯田橋) ご相談窓口 03-3265-3335